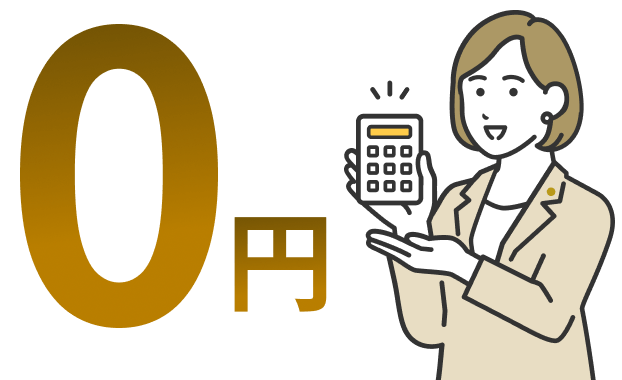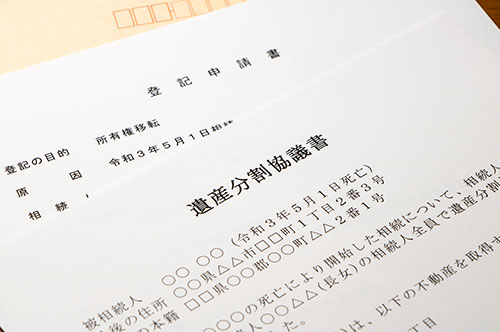知らない人から遺産相続の連絡がきた! 対応方法と注意点
- 遺産を受け取る方
- 遺産相続
- 知らない人から

突然、知らない人から「相続手続きへのご協力をお願いします」という通知が届いた場合、どうすればいいのでしょうか。相続手続きでは、印鑑証明書や実印を要求されることもあるため、新手の詐欺ではないかと不安になる方もいらっしゃると思います。
この記事では、知らない人から遺産相続に関する連絡が来る理由や適切な対処法、相続手続きに関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説していきます。


1、なぜ知らない人から遺産相続の連絡が来るのか?
突然、見知らぬ人から遺産相続の連絡がくれば怪しむのも当然といえますが、詐欺とは限りません。ここでは、知らない人から遺産相続の連絡がくる理由について解説します。
-
(1)遺産共有状態を解消するためには遺産分割が必要
被相続人が亡くなった場合、その人が所有していたすべての財産は、相続人に承継されることになります。
そして、相続人が複数いる場合には、遺産分割が行われるまで、相続財産は相続人間で共有状態となります。
相続人の間で個々の相続財産を配分し財産の帰属先を決定して、遺産共有状態を解消するためには、「遺産分割」を行う必要があります。 -
(2)遺産分割は相続人全員で行う必要がある
知らない人から遺産相続の連絡が来た場合、他の相続人が戸籍謄本などを確認した結果、あなたが相続人のひとりであったことが判明した可能性があります。
民法には、「共同相続人は(~略~)被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の分割をすることができる」と規定されています(民法第907条1項)。
すなわち、遺産分割は話し合いで行うことが原則となっています。そして、誰かひとりでも相続人が欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効であると考えられており、除外された相続人がいれば、遺産の再分割を求めることができます。
知らない人から遺産相続の連絡が来る典型的なケースとしては、以下のようなものがあります。- 被相続人が離婚している場合
- 被相続人が養子縁組している場合
- 被相続人に認知した子どもがいる場合
まず、被相続人が離婚している場合には、離婚した元配偶者との間に生まれた子どもには相続権があります。したがって、被相続人が亡くなった際には、婚姻関係にある家族とともに、元配偶者との間に生まれた子どもも相続財産を相続しているため、遺産分割協議に参加する権利があります。
また、被相続人が養子縁組をして養子をとっていたり、誰かの養子になっていたりする場合にも、養子・養親には相続権が発生することになります。
被相続人が婚姻関係によらず子どもを作り認知している場合、認知された子どもにも相続権が発生することになります。
2、知らない人から遺産相続の連絡がきたときの対処法
本章では、実際に相続の連絡が来た場合に詐欺かどうか見極める方法、相続が必要だった場合の協議の進め方などについて解説します。
-
(1)詐欺でないことを確認する
突然、「あなたは、故〇〇氏の相続人であることが判明しました」という内容の手紙が届いたら、詐欺かと疑う場合もあるでしょう。もちろん、世の中には相続に関連した詐欺の手口も存在するため、慎重に見極めることは大切です。
本当に亡くなられた方の相続人であるのかどうかは、戸籍を確認すれば分かります。通知書と一緒に相続関係説明図の写しが同封されている場合もありますが、詐欺か否かを判断するためには、ご自身で戸籍をチェックするところから始めてください。
戸籍が確認できなかったり、相続人であることが分かる資料などが何もなかったりする場合には詐欺である可能性が高いため、相手に連絡せず、不安であれば弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)相続人に連絡をして協議をする
知らない人から来た遺産相続の連絡が詐欺ではないことが分かれば、手続きを進めていく必要があります。
まずは連絡をしてきた相続人と連絡をとり、相続人全員で遺産分割の話し合い(「遺産分割協議」といいます)を進めていくことになります。正当な持ち分を求めていく場合には、この話し合いの中で適切に相手方に主張していく必要があります。
他方、相続財産について相続する権利があるとしても、縁もゆかりもない人や土地とは関わりたくないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合であっても無視して放置することは得策ではありません。関わりたくないという場合には、3章で後述するように別途「相続放棄」の手続きをとる必要があります。 -
(3)協議がまとまらない場合には遺産分割調停を申し立てる
遺産分割について相続人の間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることになります。これを遺産分割調停といいます。
遺産分割調停は、相続人のうち1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てることになります。
調停手続きでは、家庭裁判所の裁判官1名と民間人から選ばれた調停委員2名以上で構成される調停委員会が、当事者双方の事情や意見を聴取して、双方が納得して問題を解決できるよう、助言やあっせんをします。
そのため、各当事者がどのような分割方法を希望しているのかを伝えて、適切な分割案や解決のためのアドバイスを受けることが期待できます。
もし、調停での話し合いがまとまらない場合には調停は不成立として終了します。その場合、引き続き審判手続で必要な審理が行われたうえで、審判によって結論が示されることになります。
3、遺産相続の手続きにおける注意点
遺産相続の手続きを進めるにあたって注意したい「相続登記」「マイナスの財産の相続放棄」について解説します。
-
(1)古い不動産は相続登記を忘れずに
土地や建物などの不動産を相続する場合には、分割協議にしたがって、不動産登記(相続登記)をする必要があります。
何世代にわたって所有名義人を変更せずにいた古い土地である場合、いざ売却しようと思っても、売主と所有名義人が一致していなければ売ることができません。そのため、登記手続きは重要です。なお不動産登記手続きには、実印と印鑑証明書が必要です。 -
(2)マイナスの財産を相続したくない場合は相続放棄を
相続の対象となる財産はプラスの財産だけではありません。相続をすると借金や債務のようなマイナスの財産も相続人に引き継がれることになります。
被相続人が多額の借金を残しているような場合には、プラスの遺産によっては清算しきれない可能性があるため、相続放棄を検討した方がいいでしょう。
さらに、全然知らない相続人である場合や遺産のある土地が縁もゆかりもない場所である場合などでは、他人の相続トラブルに巻き込まれたくないと考える方もいらっしゃると思います。
このように相続問題からは早く手を引きたい・他の相続人と関わりたくないという場合にも、相続放棄の手続きを行うことになります。
ただし、相続放棄には期限があります。
相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に管轄の家庭裁判所に放棄の申述を行う必要がありますので注意してください。
4、遺産相続の問題で弁護士ができるサポート内容
相手が知らない相続人の場合、適切に遺産分割協議を進められるか不安な方も多いでしょう。
実際、遠方の相続人を廃除することを目的に、意図的にプラスの財産を隠す、一方的な分割案を提示する、相続放棄を要求するなどのケースもあります。
このように相続財産を隠匿されていたり、詐欺的に相続放棄の意思表示をさせられたりした場合、その後、複雑な法的トラブルに発展する可能性もあります。
したがって、相続手続きに不安があるという場合には、まずは弁護士に対応を依頼することをおすすめします。弁護士は遺産分割手続きの代理はもちろん、相続人や相続財産の調査・確定も可能です。そのため、依頼人の正当な持ち分について、他の相続人に対し適切に主張してもらうことが可能です。
仮に当事者同士の話し合いでは解決できなかった場合も、弁護士が介入することで相手方も感情的にならずにスムーズに話し合いを行うことが期待でき、遺産分割調停となった際でも、引き続き弁護士に裁判所対応を任せることができるため、依頼者様の負担を少なくすることができます。
5、まとめ
以上、いかがだったでしょうか。この記事では知らない人から遺産相続の連絡が来る理由やその対処法などについて解説してきました。
これまで全く関わりのなかった人から遺産分割協議の連絡が入る場合、相続人の範囲も多岐にわたるケースがあり、相続人の確定だけでも相当な時間を要する可能性があります。
そのような場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、ご自身は日常生活を送りながら弁護士からの適切な進捗報告・方針相談を受けながら進めていくのが良いかもしれません。
ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスには相続事件の経験がある弁護士が在籍しております。まずは、ぜひ一度ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています