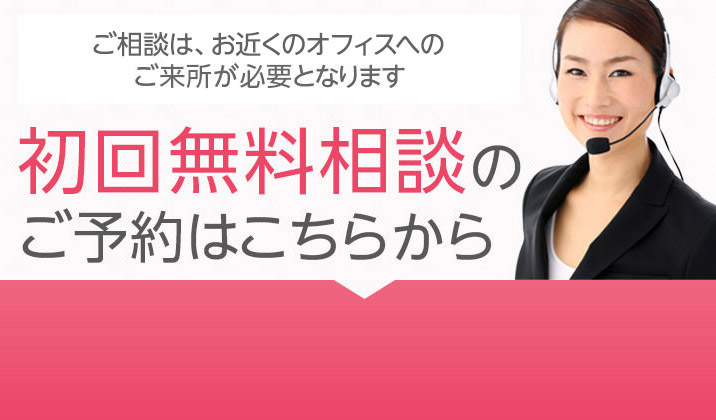離婚の調停調書とはどのようなもの? 確認点や離婚調停の流れを解説
- 離婚
- 離婚
- 調停証書

離婚調停を検討している場合、インターネット検索などで「調停調書」や「公正証書」といった言葉を目にする機会は多いでしょう。
しかし、調停調書と公正証書の具体的な内容や違いについて、よくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、離婚調停における調停調書の概要や確認すべきポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚の調停調書とは
離婚手続きにおいて、調停調書と公正証書はどちらも重要な文書です。以下では、調停調書の概要と、公正証書との違いについて解説していきます。
-
(1)調停調書とは
調停調書とは、調停において当事者双方が合意した内容をまとめた書面です。調停で成立した内容であることを証明するものであり、裁判の確定判決と同等の強い法的効力をもちます。
離婚における調停調書には、調停で取り決めた離婚内容や条件が記載されます。
一度作成された調停調書の内容は、原則として後から変更することはできません。そのため、調停で取り決める内容は慎重に判断する必要があります。 -
(2)調停調書には“強制執行”の効力がある
前述の通り、調停調書には強い法的効力があり、いわゆる“強制執行”などの効力をもちます。
離婚において強制執行がされるケースは、以下が挙げられます。
- 養育費の支払い
- 財産分与の支払い
- 慰謝料の支払い
- 住居の明け渡し
上記のケースおいて、調停調書で定めた「金額」や「支払い方法(一括や分割など)」、「退去の期日」などの内容が守られなかった場合、調停調書をもとに強制執行を申し立て、約束が実現されるよう迅速に働きかけることができます。
調停調書の法的効力については、「4、調停調書の内容が守られない場合はどうすればいい?」でも詳しく解説します。
2、調停調書と公正証書の違い
離婚に関する書類として、調停調書のほかに「公正証書」という言葉を目にするケースもあるでしょう。離婚時における調停調書と公正証書には、作成する際の離婚方法や作成場所・強制執行できる範囲などに違いがあります。
| 調停調書 | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 離婚方法 | 調停離婚 | 協議離婚 |
| 作成場所 | 家庭裁判所 | 公証役場 |
| 作成者 | 裁判所 | 公証人 |
| 権利義務の時効 | 10年間 | 10年間 |
| 強制執行できる範囲 | 記載されたすべての権利義務 | 金銭債務のみ(強制執行受諾文言の記載が必要) |
調停調書は、調停という公的な手続きによって作成され、確定判決と同様の強い法的効力をもつ点が特徴です。調停調書の内容が守られない場合、記載されたすべての権利義務に対して、訴訟手続きをせずに強制執行できます。
一方、公正証書は夫婦間の協議によって合意した内容を、公証役場で公証人に作成してもらう書面です。公正証書も、「確定判決と同一の効力を有する」(民法169条1項)ため、公正証書で約束した金銭債権の時効は、公正証書の中で支払うと約束した日から10年になります。執行受諾文言の記載があれば訴訟手続きなしで強制執行できますが、対象は慰謝料・財産分与・養育費などの金銭債務に限られます。
執行受諾文言とは、「債務を履行しない場合にはただちに強制執行を受けても異議はない」といった内容の文言です。
権利義務には時効があるため、原則として、財産分与は離婚してから2年、慰謝料は3年、養育費は5年以内に調停を申し立てるか、公正証書を作成しておかないと、支払い義務者から時効を援用されてしまい、権利行使ができなくなってしまいます。
そのため、離婚を考えている場合や、養育費や財産分与の取り決めをせずに離婚してしまった場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
3、調停調書で確認すべきポイント
調停調書は、離婚に際して夫婦間で合意した条件を証明する重要な文書です。基本的に調停で合意した離婚条件を変更するのは難しいため、事前によく確認してから判断するようにしましょう。
調停調書でとくに確認すべきポイントについて、以下でひとつずつ解説していきます。
-
(1)離婚成立の形態
調停調書には、どのような方法で離婚成立とするかが記載されます。具体的には、以下のどちらになっているかを確認するようにしましょう。
- 「申立人と相手方は、本日調停離婚をする」
- 「申立人または相手方が離婚届を役所に届け出る」
基本的には、離婚調停が成立した時点で調停離婚成立となるため、「本日調停離婚をする」といった内容が記載されます。この場合、離婚が成立した日を含めて10日以内に離婚届と調停調書謄本を役所に届け出ることも必要です。
一方で、離婚調停で離婚届を作成し、その離婚届を役所に届け出ることによって離婚を成立させる場合もあります。この方法では「協議離婚」として戸籍に記録されるため、調停離婚として記録されるのを避けるために採用されるケースがあります。 -
(2)離婚届出義務者
離婚届を役所に届け出ることによって離婚成立とする場合、離婚届を提出する「離婚届出義務者」が記載されます。
基本的には、離婚時に旧姓に戻す必要がある方が離婚届出義務者となる傾向があります。
離婚届出義務者が離婚届の提出をしなかった場合、離婚が成立しません。そのため、離婚に反対していた側が義務者とならないよう注意が必要です。 -
(3)財産分与
離婚調停で財産分与について取り決めると、財産分与の内容が調停調書に記載されます。金額や支払い方法に間違いがないかしっかり確認しておきましょう。
また、財産分与の対象に不動産や自動車が含まれる場合、名義変更の方法も記載されます。受け取る側の単独申請のほか、共同で申請しなければならない場合もあるため調停調書で確認が必要です。 -
(4)慰謝料
相手の有責行為によって離婚する場合、慰謝料を請求できます。離婚による慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるお金です。
離婚調停で慰謝料について取り決めた場合は、調停調書にその金額や支払い方法が記載されます。未払いを防ぐために、支払われなかった場合のペナルティーを設けて記載してもらうのもおすすめです。 -
(5)親権と面会交流
未成年の子どもがいる場合、親権者や面会交流の方法について離婚調停で定めておく必要があります。後から親権者を変更することは困難なため、間違いがないか確認が必要です。
面会交流については、頻度・時間・場所・方法などを具体的に決めることが重要となります。万が一守られなかった場合の対応のためにも、合意内容の確認は慎重に行いましょう。 -
(6)養育費
未成年の子どもがいる場合は、離婚調停の場で養育費の取り決めも行います。財産分与や慰謝料などと同様に金銭的な条件であるため、金額や支払い方法について確認が必要です。
養育費の支払いは子どもが20歳になるまでとするのが一般的ですが、明確に規定があるわけではありません。子どもの生活や未来にかかわる条件であるため、慎重に判断しましょう。
4、調停調書の内容が守られない場合はどうすればいい?
離婚調停が成立して調停調書が作成されたとしても、必ずしも相手がその内容を守ってくれるとは限りません。たとえば、養育費の支払いが滞ったり面会交流に応じてくれなかったりする可能性もあります。
調停調書の内容が守られない場合はどのように対応すればいいのか、以下で具体的に確認していきましょう。
-
(1)相手への連絡
調停調書の内容が守られていない場合、まずは相手に連絡して調停調書に違反していることを伝え、履行を促します。
連絡する際は証拠が残る連絡手段として、内容証明郵便を利用するのが有効です。内容証明郵便とは、いつ誰がどのような内容の文書を送ったのかを郵便局が保管・証明してくれるサービスです。
内容証明郵便を送ることで心理的なプレッシャーを与えられるため、相手方が履行に応じる可能性があります。 -
(2)履行勧告・履行命令
相手と連絡が取れない場合や、連絡しても対応されない場合は、「履行勧告」や「履行命令」を行いましょう。
履行勧告とは、家庭裁判所から相手に対して調停調書の内容を守るように促す手続きです。あくまでも勧告であるため、強制的に支払わせることはできません。
一方で履行命令とは、履行勧告に従わない相手に対して家庭裁判所が期限内の履行を命じる手続きです。正当な理由なく履行命令に従わなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。 -
(3)強制執行
履行勧告や履行命令に相手が従わない場合、強制執行の手続きができます。
離婚調停調書における強制執行とは、離婚調停で取り決めた権利義務を強制的に実現させる手続きです。たとえば、養育費の未払いが続いている場合、強制執行によって相手の給料や預貯金を差し押さえて支払いを確保します。
ただし、強制執行で給料や預貯金を差し押さえたとしても、仕事を辞められたり口座に預金がなかったりする場合もあります。強制執行の手続き自体が空振りになってしまう可能性も考慮した上で、最終手段として検討するようにしましょう。
5、まとめ
離婚調停は、家庭裁判所を介して、適切な条件での離婚を目指す手続きです。合意した内容を、調停調書に正しく反映させることで、後々のトラブルを未然に防げる可能性が高まります。
調停調書には、協議離婚の際に作成する公正証書よりも強力な法的効力があります。履行勧告や強制執行が必要になった場合もスムーズに手続きが行えるため、記載内容はしっかりと確認しておくようにしましょう。
離婚調停の進め方や離婚条件について不安がある方は、ベリーベスト法律事務所
豊橋オフィスの弁護士にご相談ください。離婚トラブルについて実績がある弁護士が、お一人おひとりの状況に合わせてサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています