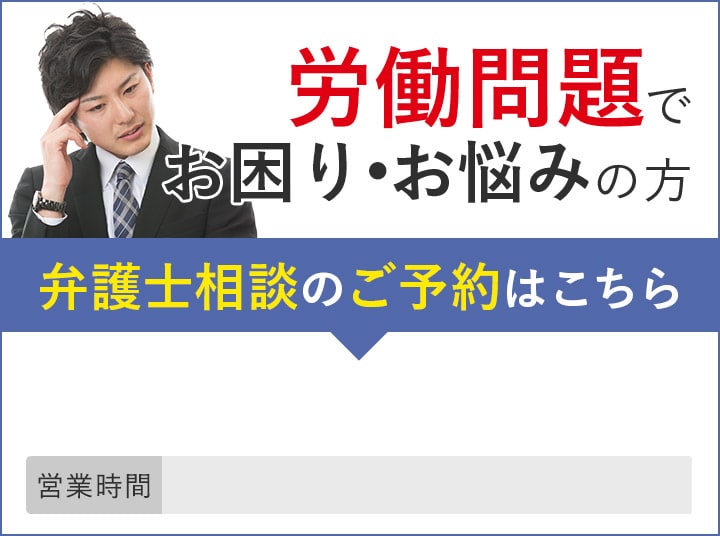ブラック企業を辞めたい! 退職方法や残業代請求について解説
- その他
- ブラック企業
- 辞めたい

愛知県庁が公開する「あいちの勤労(令和2年年報)」の統計データによると、雇用期間の定めがない労働者1人あたりの総労働時間は、138.1時間(調査産業計での平均月間)でした。このうち、所定外労働時間は11.7時間です。
多数ある企業の中には、違法かつ劣悪な労働環境で、いわゆる「ブラック企業」と呼ばれるようなところもあります。そのような企業を辞めたいと思うのは、おかしなことではありません。
ブラック企業を辞めようとした際には、企業側がさまざまな手段で引き留めようとしてくるケースもありますが、屈することなく、退職を決行しましょう。
今回は、ブラック企業を辞めたいと考えた場合に知っておくべき注意点や手続きのことなどについて、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士が解説します。
目次


1、ブラック企業によく見られる特徴
ブラック企業は、労働基準法違反などの違法行為が常態化しており、労働環境が非常に劣悪なことがあります。最初に、厚生労働省のQ&Aでも挙げられている例を含めて、ブラック企業の特徴を紹介します。
-
(1)極端な長時間労働や重すぎるノルマを課す
労働基準法では、労働時間の上限に関する厳格なルールが定められていますが、ブラック企業はそのルールを無視して、労働者に極端な長時間労働を強いるケースが多いです。
また、明示的に「残業しろ」とは言わずとも、重すぎるノルマを課すことによって、過酷に働かざるを得ない状況に追い込む例もよく見られます。 -
(2)残業代を正しく支払わない
労働基準法のルール上、労働者が時間外労働・休日労働・深夜労働を行ったら、その分の残業代は支払われなければなりません。
しかし、ブラック企業は勤怠管理をきちんと行わず、働いた時間に見合った残業代を支払わない(=サービス残業を強制する)ことがあります。<残業代が発生する労働>- 時間外労働:法定労働時間を超える労働
- 休日労働:法定休日の労働
- 深夜労働:午後10時から午前5時までに行われる労働
特に、定時に退勤の打刻をさせたうえで、その後も働かせるようなブラック企業は非常に悪質です。
-
(3)ハラスメントが横行している
男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法により、企業には、社内におけるセクハラ・パワハラの防止措置を講ずることが義務付けられています。
ブラック企業では、適切な防止措置を講ずることなく、悪質なハラスメントを黙認している場合が多いです。その結果、社内でハラスメントが横行し、労働者が短期間で離職するため、人材が定着しない傾向にあります。 -
(4)労働者を過度に選別する
一般的に、労働者は能力に応じて昇給したり昇格したりするものです。
違法・不適切な方法によって、企業側が労働者間の競争を促しているのであれば、問題があるといえます。
たとえば、違法残業の時間数で昇給・昇格する労働者を選別したり、過酷すぎるノルマを課したうえで達成を競わせたりするのは、ブラック企業に見られる特徴でしょう。 -
(5)労使協定や就業規則が公開されていない
企業には、労働者に対して労使協定や就業規則の内容を周知させることが義務付けられています(労働基準法第106条第1項)。これらのルールは労働条件に直接関わるため、労働者に周知させて透明性を確保しなければなりません。
ブラック企業では、労働条件について労働者に疑問を持たせないようにするためか、労使協定や就業規則を非公開としているケースがありますが、明確な労働基準法違反です。 -
(6)有給休暇の取得を断られる
有給休暇は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、労働者が請求した時季に与えられなければなりません(労働基準法第39条第5項)。
労働者を1日でも多く働かせるために、合理的な理由なく有給休暇の取得申請を拒否する例がブラック企業では続発しています。 -
(7)休憩時間中も仕事をしなければいけない
企業は、休憩時間を労働者の自由に利用させなければなりません(労働基準法第34条第3項)。
しかしブラック企業は、休憩時間であるにもかかわらず業務を強制し、労働者に息つく間も与えずに仕事をさせる傾向にあります。 -
(8)休日も頻繁に出勤させられる
企業が労働者に休日出勤を命じることができるのは、労使協定(36協定)が締結されており、かつ36協定の上限時間に収まる場合のみです。
ブラック企業は、36協定のルールを無視して休日出勤を強制し、さらにその分の残業代を支払わないという特徴もあります。
2、ブラック企業を辞めたい場合の準備・手続き
ブラック企業を辞めるに当たって、特別な準備は必要ありません。
働くのがつらいときには、ご自身の心身を守るために、一刻も早く退職届を提出しましょう。
民法627条では、退職届を提出するなどの退職の意思を示してから2週間を経過すると辞めることができる、と定められています。就業規則などで2週間よりも前に予告期間が定められているケースもありますが、そのような規定は無効の可能性が高いです。
また、給与収入がなくなるとしても、雇用保険を受給すればある程度カバーすることができます。
このように、ブラック企業を退職することのハードルは、決して高いものではありません。
ただし、企業に対する残業代請求を検討している場合には、残業をしたことの証拠が必要になるため、在籍中に可能な範囲で集めておくことがおすすめです。どのような証拠が効果的であるかは、この後に続く4章で解説します。
なお、ブラック企業を辞めたいと思っていても、自分でその意思を伝えることが難しいという場合は、弁護士による退職サポートの利用もひとつの選択肢です。
弁護士は、ご本人の代わりに退職の意思を企業に伝えるほか、未払い残業代の請求や交渉などについても、一括して代行することができます。
3、ブラック企業に退職を伝える際の注意点
退職届を提出するなど、労働者が企業を辞めるための意思表示をすると、ブラック企業はさまざまな手段を用いて退職を妨害してくることがあります。労働者は、そのような妨害工作に惑わされることなく、退職の意思を貫きましょう。
-
(1)企業からの脅しに屈しない
企業を辞めたいと伝えたとき、企業側から脅迫されたり侮辱されたりするケースがあります。
「退職したら損害賠償を請求する」
「退職するような無能な人間は、他の企業に行っても通用しない」
ブラック企業からこのような脅しを受けたとしても、屈することのないようにしてください。
労働者は、企業を退職することで損害賠償責任を負うことはありません。また、企業が労働者を罵倒することは、名誉毀損罪・侮辱罪などの犯罪や、民法上の不法行為に該当する可能性があります。
ブラック企業の脅しは不合理・違法なものとして受け流し、決然と退職の意思を貫きましょう。 -
(2)退職届に「受理」は不要
ブラック企業は、退職届を受理しないという対応に出るかもしれません。
しかし、退職届は「受理」される必要はなく、企業側に退職届が到達してから2週間が経過すると、そのまま退職の効果が発生します。そのため、ブラック企業が退職届の「不受理」を主張しても、無視して退職することが可能です。
なお、企業側への到達日を明確化するために、退職届は内容証明郵便やメール等の記録の残る方法で送付することをおすすめいたします。 -
(3)雇用保険の受給で企業が協力してくれないことがある
ブラック企業は、退職した労働者が雇用保険を受給するための手続きについて、離職票を発行しないなどのように非協力的なケースが多いです。
しかし、企業の協力が得られないために必要書類がそろわなくても、ハローワークは代替書類などで対応してくれる場合があります。
そのため、企業から「退職しても雇用保険は受給させない」などと脅されても不安に思わず、かまうことなく退職してください。
4、未払い残業代を請求するための手続き・ポイント
ブラック企業を退職する段階で、未払い残業代が発生しているケースがあるでしょう。
未払い残業代を企業に対して請求する場合、以下のいずれかの方法で手続きを行います。
企業側と直接話し合って、未払い残業代の精算を行います。
● 労働審判
裁判所で行われる非公開の労働審判手続きを通じて、未払い残業代の精算を行います。原則として3回以内で審理が終結するため、迅速な解決が期待できます。
● 訴訟
裁判所の公開法廷で行われる訴訟手続きを通じて、判決に基づき未払い残業代を精算します。残業代の問題を終局的に解決できます。
いずれの手続きによる場合でも、以下のような残業の証拠を十分に集めることが、残業代請求を成功させるためのポイントです。
- タイムカードや勤怠管理システムの記録
- オフィスの入退館履歴
- 交通系ICカードの乗車履歴
- 業務上やり取りしたメールの内容や日時
- 業務日誌
ブラック企業は、労働者からの交渉に素直に応じてくれるとは限りません。
そのため、交渉・労働審判・訴訟の対応は、弁護士にまとめて依頼するのが安心です。弁護士は、法的な知識と経験をもとに、労働者に有利な形で企業とのトラブルを解決できるようにサポートいたします。
ブラック企業に対する未払い残業代請求の際は、弁護士にお任せください。
お問い合わせください。
5、まとめ
劣悪な労働環境は、社員の心身に大きな悪影響を及ぼします。ご自身を守るためにも、「辞めたい」という気持ちを行動に移し、別企業への再就職を目指す転職活動を始めていきましょう。
ベリーベスト法律事務所は、退職代行から未払い残業代の請求まで、労働者がブラック企業を円滑に退職できるようにサポートいたします。
ブラック企業を辞めたいとお考えの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています